(この記事は約 6 分で読めます。)

交通事故に遭遇すると、被害者(又は遺族)は加害者に対して損害賠償請求をする事になります。一方で、被害者は加害者以外からも香典や見舞金、所得補償保険金などを受け取る事が有りますよね。
被害者が加害者以外から利益を得た場合は、損害額からその利益を控除して損害賠償金を計算する(「損益相殺」といいます)事になるのですが、どの様なものが利益から控除されるのでしょうか?
また、被害者の得た利益が全て控除される訳ではなく、控除の対象にならないものも有ります。
そこで、ここでは被害者が受け取ったとしても損益相殺として損害賠償金額から「控除されるもの・されないもの」について、以下でまとめて見ていきます。
損益相殺するもの
以下では、損益相殺として損害賠償金額から控除されるものについて見ていきましょう。
なお、基本的に被害者が受けた損害を填補(てんぽ)するものであれば、損害賠償額金額の計算上控除される事になります。
受領済みの自賠責保険金や政府保障事業による填補金
自賠責保険からの支払金は、被害者に対する損害の填補そのものなので損害額から控除される事になります。
また、政府保障事業制度は自賠責保険から支払がされない事故(※)から被害者を守る制度ですが、これも損害の填補そのものなので損益相殺の対象となります。
※:自賠責保険に加入していない車との事故や、盗難車など自賠責保険の被保険者でない方が運転していた際の事故
受領済みの労災保険法に基づく給付金

労働者災害補償保険法(労災保険法)で規定されている以下の様な保険給付については、原則として損害額から控除される事になります。
- 長期傷病補償給付金
- 障害補償年金
- 休業補償給付金
- 傷病補償年金
- 遺族(補償)年金
注:社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業)から支払われる特別支給金については、控除されません。
これは、保険者である国が損害賠償請求権を代位の規定(同法12条の4第2項)によって取得するので、被害者がその分の損害賠償請求権を失うからです。
なお、控除対象となるのは現実に支払われた金額ですが、未給付だったとしても「支払を受ける事が確定した分(※)」については控除出来るとされています(最大判平5年3月24日民集47巻4号3039頁)。
※:「支払を受ける事が確定した」とは「具体的な支給金額が確定し、支払手続きをとる事が確定したとき」を意味しています。
休業補償給付金や傷病(障害)補償年金は逸失利益に関する補償金です。従って、被害者の損害額を超える給付金が有ったとしても、超過額を他の積極損害や慰謝料から差し引きする事は出来ません。保険会社が勝手に差し引きしているケースも有る様なので、注意して下さいね。
受領済みの厚生年金法等に基づく給付金

厚生年金法等の公的年金や公的医療保険制度は、労災保険同様に代位規定が有るので損害額から控除されます。
参考:「支払を受ける事が確定した分」については未受給でも控除対象です。
実務上は医療費負担に関して給付された分を損害賠償請求金額から除外するので、損益相殺で問題になる事は殆ど有りません。
参考に、同様の扱いを受ける給付金には以下の様なものが有ります。
厚生年金保険法に基づく給付金
- 障害年金給付金
- 遺族(補償)年金
国民年金法に基づく給付金
- 障害年金給付金
- 母子年金
国家公務員災害補償法に基づく給付金
- 災害補償年金
- 療養補償給付金
地方公務員等共済組合法に基づく給付金
- 遺族年金
所得補償保険金

所得補償保険金は、被保険者の傷害や疾病そのものに対してではなく、事故により被った「就業不能」という損害を填補するための保険です。従って、既に受け取った保険金については損益相殺として控除されます(最判平元1.19判事1302号144頁)。
保険金が支払われた場合、保険会社は支払った金額の限度内で加害者に対する休業損害の賠償請求権を取得する事になります(商法662条・保険法25条)。従って、保険会社が損害賠償請求権を行使するかどうかは別として、被保険者は損害賠償請求権を喪失すると考えられるので、損害の填補と考えるのが相当という訳ですね。
参考:「無保険車傷害保険(特約)」の保険金についても、所得補償保険金と同様に損害額から控除されます。
損益相殺するものに対する総括・まとめ
上記で紹介したものは、事故後に受け取ると損害賠償金額を算定する際に控除される事になります。
とはいっても、損害賠償金として受け取る事が出来たものを形を変えて受け取ったに過ぎません。控除されるからといって損をする訳ではないので心配は不要です。
損益相殺しないもの
以下では、給付を受けても損益相殺として損害賠償金額から控除されないものを見てみましょう。
なお、基本的に被害者の得た利益が損害を填補(てんぽ)するものでなかければ、損益相殺の対象とはなりません。
香典

社会通念上、香典は損害の填補と見られないので、一般の会葬者から受け取った分については控除されません。但し、加害者側から香典を受け取った場合、その金額が社交儀礼を超えた金額であれば弁償の一部として控除される事が有ります。
とはいっても、損害を与えた加害者が被害者に対して支払う香典は、一般の方からもらう金額と比べると高くなりがちですよね。従って、多少高かったからといって即座に「社交儀礼を超えた」とはなりません。
中には、香典として100万円受け取っていても「被害者の精神的苦痛の一部を償うためのもの」として損害の填補としての性質を否定した例も有る様です(東京地判平7・7・26交民28巻4号1101頁)。
見舞金

見舞金も香典同様に、社会通念上は損害の填補と見られないので小額であれば控除されません。但し、社交儀礼を超えた金額の場合は慰謝料の一部として控除される事が有ります。
とはいっても1万円や2万円であれば、問題無く社交儀礼の範囲内とされるでしょうね。
ちなみに、30万円の見舞金を渡したケースで「被害者感情を軽減させる為のものとしては高額なので損益相殺の対象とした」という判例が有ります(大阪地判平5・2・22 交民26巻1号233頁)。
生命保険金や付加特約に基づく入院給付金等
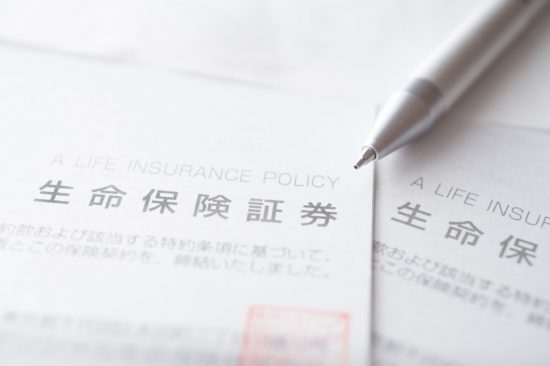
生命保険金や付加特約に基づく入院給付金等は、被害者自身が掛金を支払っていたもので「掛金の対価」として支払われます。
死亡の原因が病気であろうが交通事故であろうが保険金は支払われるので、たまたま交通事故によって死亡したからといって損害賠償額から控除すべきではありません。
従って、損益相殺はされません(最判昭39.9.25民集18巻7号1528頁)。
搭乗者傷害保険金
搭乗者障害保険は、契約車両に乗っていた方が事故で死傷した場合に予め設定した定額の保険金が支払われるものです。従って、損害を填補する性質が無いので控除出来ません(最判平7・1・30民集49巻1号211頁)。
参考:保険会社が保険金を支払っても、被保険者の相続人が加害者に対して有する損害賠償請求権を代位取得する事も有りません。
但し、加害者が保険料を負担していた場合は、慰謝料を減額する方向で斟酌する事が出来るとしている判例も有る様です。
生活保護法による給付金

交通事故の被害者が生活保護受給者の場合、被害者は損害賠償請求権という資産を持っているものとして扱われます。
従って、本来は生活保護費の給付対象ではなく、窮地の状態から救う為に仮支給するものと考えられるので、「賠償金が支払われたら生活保護の給付金は返還する」という扱いがされています(生活保護法第63条)。
従って、生活保護法による給付金を受け取っても損害額からの控除はされません(最判昭46.6.29民集25巻4号650頁)。
損害賠償金に対する税金

交通事故の被害者は、交通事故に遭うこと無く生活をしていれば、自分が得た収入から税金を払う事になります。一方で、損害賠償金は「損害の填補」としての性質が有るので、所得扱いされず非課税です。
非課税のものから税金を控除して損害賠償金額を算出すると、損害賠償金額が税金分減るので「加害者が得をする」という結果になります。従って、加害者が得をするよりは被害者が得をした方が合理的という理由から、損害賠償金から税金分の控除はされません。
なお、高額所得者の場合は「被害者の利得が大きくなるので不合理」という考えから、税金の控除をしない代わりに生活費割合を高めに認定する、といった配慮がなされる事も有ります(最判昭45.7.24民集24巻7号1177頁)。
未受給の労災保険金・厚生年金・共済年金等

労働者災害補償保険法(労災保険法)で規定されている保険給付については、原則として損害額から控除されます。
但し、以下の様に「労働福祉事業の一貫として支給されるもの(労災保険法第23条)」については、通常の保険給付と性質が異なる(※)ので損害額からの控除はされません。
※:通常の保険給付は、保険者である国が損害賠償請求権を代位の規定(同法12条の4第2項)によって取得するので、被害者がその分の損害賠償請求権を失います。しかし、特別支給金については代位の規定が有りません。
- 労災保険法による特別支給金
- 特別年金休業特別支給金
- 障害特別支給金
- 障害特別年金
- 遺族特別支給金
- 遺族特別年金
- 労災就学援助金
なお、控除されるのは示談成立(若しくは判決)までに受け取った分(※)で、未受給のものは控除されません。これは、厚生年金や共済年金等の給付金についても同様です。
※:具体的な支給金額が確定し、支払手続きをとる事が確定した分については、未支給でも控除されます。
損益相殺しないものに対する総括・まとめ
上記で紹介したものについては、交通事故後に受け取ったとしても加害者からの損害賠償金額に影響を与えません。
「影響を与えないから得」というものでもないですが、知識としては知っておいた方が良いでしょうね。

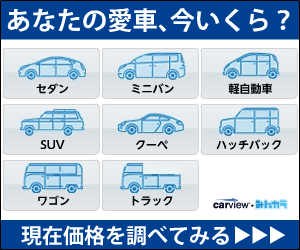




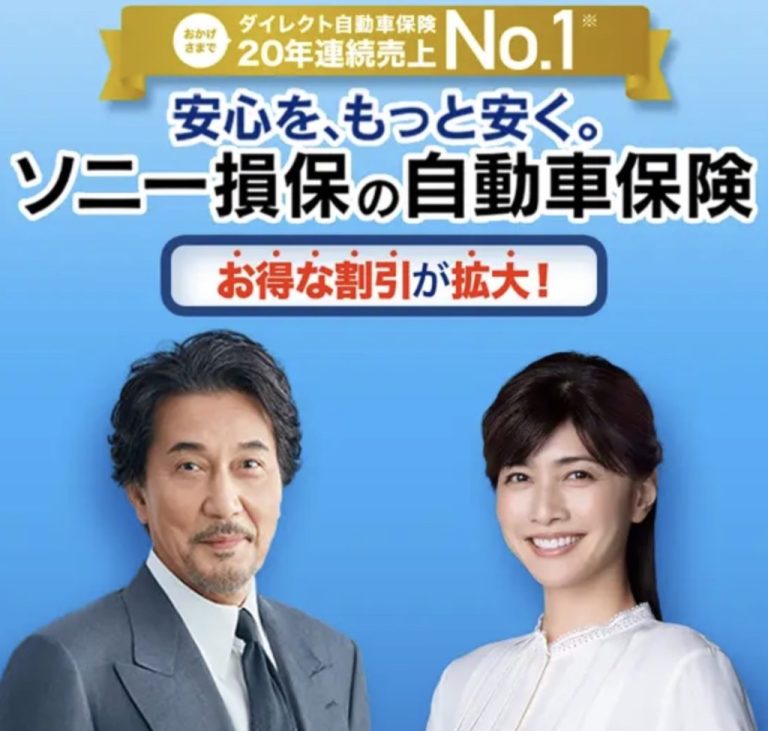




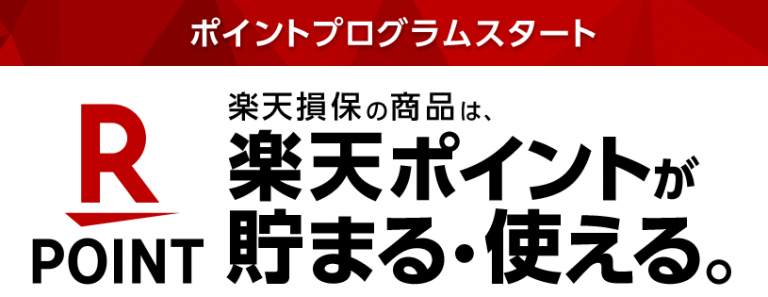







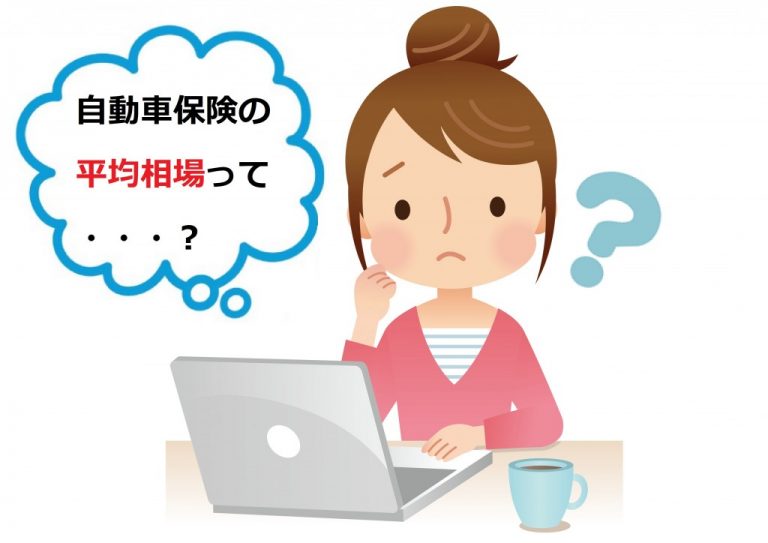


関連記事をチェックする