(この記事は約 3 分で読めます。)
交通事故で被害者が受け取る損害賠償金を計算する過程で、「労働能力喪失期間」という概念が出てきます。
被害者が後遺障害によって事故以降働く事ができなくなってしまった場合、減収分を逸失利益として加害者に請求することになります。この逸失利益を計算するには、被害者の「失った収入」と「事故により働けなくなった期間」の情報が必要となります。(参考記事:後遺症による逸失利益【総論-弁護士基準】)
ここでは労働能力喪失期間の考え方について見ていきましょう。なお、似て非なる概念として就労可能年数がありますが、就労可能年数については別途「就労可能年数の計算方法~平均余命と67歳とどっちで考えるべき?」で解説しているので参考にしてください。
労働能力喪失期間の認定
後遺障害の逸失利益を計算する場合、一般的に「症状固定時の就労可能年限」が労働能力喪失期間として扱われます。例えば、四肢切断や機能障害、脳外傷による神経機能障害などの後遺障害については、就労可能年限までの年数を労働能力喪失期間として扱う判例が多いです。
なお、就労可能年限は通常は67歳となっており、事故時に高齢だった場合は平均余命の2分の1までの年数です。しかし、以下の様に原則と異なる考え方をする場合もあります。
非器質性精神障害の場合
非器質性精神障害は、脳組織に器質的異常(物理的な損傷など)が確認できないものの、異常な精神状態が発生している事を言います。強烈なショック体験や精神的なストレスが記憶から離れず、時間が経っても恐怖を感じる「PTSD」や「うつ状態」のことなどを指しています。
この非器質性精神障害は、一般的に治療により回復可能なものとして扱われ、労働能力喪失期間を短く認定される傾向にあります。
①PTSDの主婦兼看護助手の事例。10年間14%の労働能力喪失を認めた例。
②固定時38歳の主婦の事例。非器質性精神障害は適切な治療等で将来軽減されることが期待されるものの、事故後5年経過しても回復の兆候がないことも考慮して、15年間14%の労働能力喪失を認めた例。
軽度の神経機能障害の場合
軽度の神経機能障害は「自覚症状を主体とする障害のため、労働能力喪失期間を決定するのが難しく、短期間に制限するべきである」という考えがあります。
そこで、骨折後の疼痛や末しょう神経の圧迫が確認できる場合などを裏付ける所見の有無によって、期間の長短が決まる傾向にあります。
むちうち損傷の場合
むちうち損傷の場合、従来は労働能力喪失期間が短く認定されがちでしたが、最近は後遺障害等級によって、労働能力喪失期間の長短が異なる認定を受ける傾向にあります。
詳細は別途「むちうち後遺障害としての損害請求」で説明しているので、参考にしてください。
事故後に死亡した場合
交通事故後に後遺障害とは関係の無い病気や事故が原因で死亡したり、自殺することが有ります。この場合は、近い将来に死亡することが客観的に予測されているなどの事情がない限り、死亡の事実は考慮しないことになります。なぜなら、交通事故によって既に労働能力が現に喪失されており、その後の事由によって当初の内容が変わるべきではないからです。
従って、就労可能年限までを労働能力喪失期間として損害の計算をすることになります。
事故後自殺した男性の事例。事故と自殺の因果関係は否定し、予想される後遺障害による逸失利益として、賃金センサス平均賃金を基礎に、労働能力喪失率を27%とし、67歳までの逸失利益を認めた例。
ところで、死亡すると、当該死亡者の将来の生活費が不要になります。上記の様に死亡しなかったものとして就労可能年限までの喪失期間を認めると、被害者側に不当に利益が生じる様にも思えますよね。しかし、不法行為によって利益を得ている訳ではないので、不要となった生活費の控除はしないことになっています。
一方で、将来の介護費用については支出の必要性がなくなるので、損害賠償請求は出来ません。
会社員の男性が頸椎捻挫等の後遺障害を認定されたものの、障害と因果関係がない疾患によって死亡。死亡後の将来治療費を支出する必要が無くなったので損害賠償請求ができないとした例











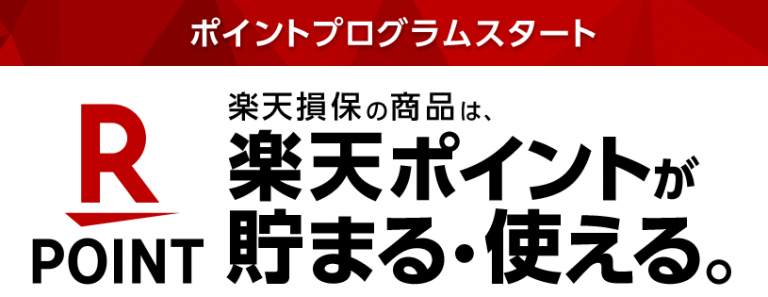


















コメント
この記事へのコメントはありません。