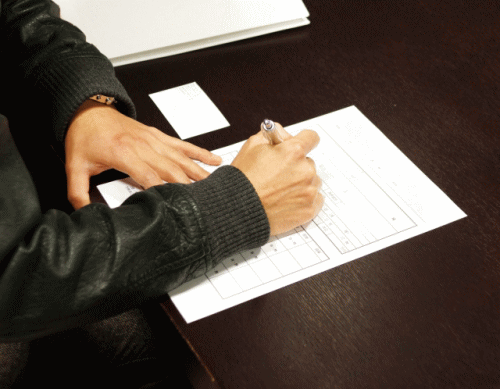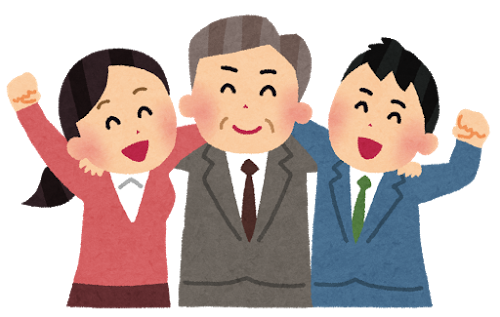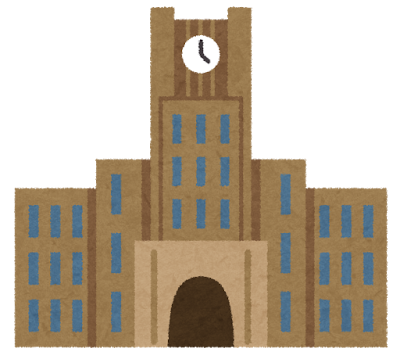この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
交通事故の被害者に事故当時収入があった場合、「受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額」が休業損害として認められることになります。
しかし、事故当時被害者が無職だった場合は収入がないので喪失した収入額はありません。
果たして失業者に休業損害は認められるでしょうか?
原則:休業損害は認められない。
失業中の人に対しては、原則として休業損害は認められません。
失業中という事は収入がないことが前提なので、休業損害を算定しようにも、計算の元となる収入金額がないから仕方ありませんね。
特に、ケガが治り働くことが出来るようになるまでの期間が比較的短期の場合は、休業損害の発生が否定されることが多いです。
例外:休業損害が認められる場合
上記の様に原則的には失業中の場合は休業損害は認められません。
しかし、失業中であっても労働能力や労働意欲があり、事故前から内定が出ていた場合や、事故にあっていなければ治療期間中に就職できたと考えられる場合は、休業損害が認められる可能性があります。
また、たとえ事故当時に失業中だったとしても、休業期間が長い場合にずっと無職であるとは断定できません。
従って、治療に長期間がかかる場合は休業損害が認められることも多いです。
休業損害をどの時点から認めるかは裁判で決まっていく事になりますが、基本的には失職の経緯や年齢、技能、資格などを考慮して時期を認定することになります。
休業損害を認める場合、基礎収入額にどの金額を採用するかを考える必要があります。
就職先から内定が出ていた場合は、予定されている給与額を元に算定されます。
一方で、内定が無く将来得られる収入の目安となる金額がない場合、失職前の収入・失職の経緯・年齢・技能・資格を考慮し、賃金センサスの平均賃金を参考に収入を推測することになります。
ただし、前職では給料が良かったけど転職先では給料が下がったということもあり得ます。
また、元々賃金センサスよりも収入が低かった方の場合、転職したとしても賃金センサス水準の収入を得られるとは限りません。
そこで、被害者毎に背景や状況を考慮して現実的な金額を認定していくことになります。
①無職の男性の事例。
大卒であり、事故当時無職だったが事故の1ヶ月後からソフトウェア関連会社を設立し代表取締役になる予定だったため、賃金センサス(男性・大卒・全年齢)平均賃金を基礎に算定した例
②調理師資格を有し求職中の男性の事例。
前職離職時の収入により休業損害を算定すべきであり、これよりも高額な賃金センサスを使用するのは相当ではないとした例。
③事故時定職が無かった大卒派遣社員の事例。
事故前は派遣社員として働いており、事故当時は定職に就いていなかったが、家事労働の一部を負担しつつ将来的には就職することを希望していた。
そこで事故当時の賃金センサス(女性・学歴計・全年齢)平均賃金の5割相当を基礎収入として認めた例
④有名市立大学を卒業し、証券会社に就職後MBAを取得した男性の事例。
再就職が内定し、年棒1,500万円と成果報酬ボーナス・ストックオプションの付与が条件となっていた。
事故により内定を辞退した場合に、休業損害の基礎額を1,500万円とすることは合理的であるとした例
総務省統計局が発表している労働力調査によると、過去の完全失業率(15歳以上の働く意欲のある人労働力人口のうち、職がなく求職活動をしている人の割合)は2011年4.6%、2012年4.3%、2013年4.0%と減少傾向にあります。
景気が徐々に上向きになり、働けるのに働いていない人の数が減少して来ていることを示しているので、完全失業率が下がっていく事はいい傾向ですね。